抗血栓薬は標的によって使用する薬が違います。
血栓の種類
白色血栓:血小板によって作られる血栓(抗血小板薬)動脈硬化などの狭窄部に生じやすい。
薬剤:アスピリン、クロピドグレルなど
赤色血栓:フィブリンによって作られる血栓(抗凝固薬)心房細動・静脈など血液の停滞で生じやすい。
薬剤:ワーファリン、DOACなど
今回の記事は抗血小板薬について記載します。
血小板とは
血小板は直径3μm程度の血球成分です。赤血球の半分以下の大きさです。
血小板は出血などにより発生した刺激を受けると凝集し止血に働きます。
血小板が凝集する刺激:ADP、血小板活性因子、トロンボキサンA2、トロンビン
刺激を受けると血小板内のカルシウムイオンが増加し凝集します。
抗血小板薬
アスピリン(COX(シクロオキシゲナーゼ)阻害剤)
トロンボキサンA2の合成を阻害することで血小板の凝集を抑制します。
トロンボキサンA2のみでなくプロスタグランジン生成も抑制されるため副作用が生じる可能性があります。
副作用:胃腸障害、嘔吐、蕁麻疹、発疹、浮腫、眩暈、頭痛、興奮、過呼吸、倦怠感、貧血
胃腸障害:プロスタグランジン合成抑制により胃酸を中和する粘液の分泌が低下する。
蕁麻疹・発疹:薬に抵抗できずアレルギー類似の症状が生じる。アレルギーのようにIgE抗体反応では なく、プロスタグランジンとロイコトリエンのアンバランスにより生じる。
浮腫:プロスタグランジン抑制のため腎動脈の収縮が持続し腎血流量が減少する。そのため水分とナトリウムの再吸収が亢進し浮腫が生じる。
クロピドグレル(ADP阻害薬)
血小板表面に存在するADP受容体を阻害します。その結果アデニル酸シクラーゼという酵素の働きが促進されcAMPが増えます。cAMPが増えると血小板内のカルシウムイオンが低下し血小板の凝集を阻害しします。
クロピドグレルは肝臓で代謝を受けることで薬効を発揮します。以前はシトクロムP450という酵素によって代謝されると考えられていましたが、現在はパラオキソナーゼという酵素に代謝されると考えられております。
パラオキソナーゼ:肝臓で発現する酵素。薬剤中のエステルという構造を加水分解するエステラーゼの一種です。
肝硬変などの肝臓疾患患者ではクロピドグレルの代謝が減少し薬効を発揮できないことがあるようです。
副作用:下血、吐血、視力低下、関節痛、疲労感・倦怠感、食欲不振、黄疸

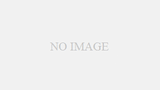
コメント